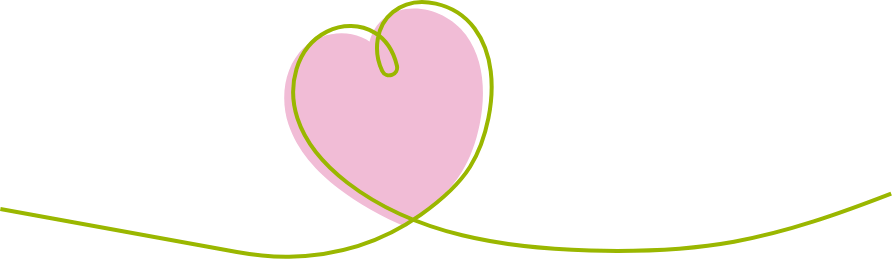42歳での昇格、せっかく軌道に乗ってきたことろだったのに~脳梗塞で右半身に後遺症が残った母親の話~
「母さんが倒れた!?」
青森に住む親戚の叔父からの連絡で、俺は思わず職場で声を荒げてしまった。
なんでも、今日の昼間に母のいる実家へ会いに行ったのだという。
事前に連絡をとっていたので家にいるはずだが、チャイムを押しても返事がなかったので家に上がったところ中で倒れていたらしい。
急いで救急車を呼び、今病院に搬送されたところだと叔父さんは動揺を押し殺したような声で電話をしてきてくれた。
『タカシ、今から帰ってこれるか?』
「え、今から…」
「帰ってあげなさい」
問いかけに対し素直に頷けないでいたところで、隣で様子を伺っていた上司から許しを得たので「帰るよ」と返事をしてひとまず電話を切った。
「実家、たしか青森だったよね…お母さまの容体はどうって?」
「家で倒れていたことろを叔父が発見してくれたみたいで、今救急車で運ばれたそうです」
それ以外はまだ…と答える俺に、「1週間とりあえず休んでいいから」と配慮をしてもらえた。
「申し訳ありません、ありがとうございます」
そこから俺は急いで自宅へ帰り、簡単に荷物をまとめた。
東京から青森の実家までは飛行機を使う必要があるので、チケットの手配もしつつ羽田空港へ向かうまでの経路をスマホで調べる。
すると再度電話が鳴った。
「もしもし」
『おお、お前の母さんだけどな…命に問題はないそうだ。ただ脳梗塞だと言われた』
あと少し発見が遅れていたら危なかったらしい。
その言葉を聞いてぞっとしてしまった。
叔父さんがたまたま家に行ってくれていなかったらと思うと、背筋が凍る。
ひとまず無事でよかった…
「すみません、吉井ですが」
なんとか当日中に青森に着き、運ばれた病院の窓口で名前を告げると優しそうな看護師さんが母親の病室まで案内してくれた。
「意識は戻られています。あとで先生から詳しい症状を話してもらいますね」
「ああ、わかりました。お世話になります」
そう言って俺は病室の扉に手を掛ける。
「母さん、入るよ」
ふわりと消毒液の匂いがただよう病室のベッドには、しばらく見ない間に少し痩せた母親が横たわっていた。
「タカシ、久しぶり…迷惑かけたわね」
「本当だよ…」
「母さんね、右半身がマヒするかもって言われたの。だから、もう今までの生活には戻れないかもしれない」
それは“介護”を意味する言葉だと鈍感な俺でもわかった。
「そっ…か。これから、どうしようか」
俺はまだ東京で仕事がしたい、やっと社内で役職のある地位まで昇格できたんだから。
「本当は施設がいいと思うんだけど…やっぱり高いからね…」
“私の貯金では難しい”
つまり、自宅での介護が必要になる。そう言われているようだった。
「少し、考えさせてくれ」

俺は今年で42歳、母親は76歳。
兄妹はおらず父親もとうに亡くなっていて、頼れる人といえば先ほど連絡をくれた叔父さんくらいだろう。
でも親戚にまで迷惑はかけられない。
___それから数か月後。
俺と母さんは話し合った結果、青森の実家で一緒に暮らすことを決めた。
マヒしてしまった右半身は少しずつ快方に向かっているが、年齢的に全快は望めないだろうと医者に言われたので平日はヘルパーさんの力も借りることになっている。
せっかく手に入れた職場での地位も手放し、新しい環境での再スタートとなったことが一番の気がかりだった。
しかし、身内は俺一人しかいないので背に腹は代えられない。
「じゃあ、今日もお願いします」
「はい、お任せください」
平日は仕事、土日は介護。
40代にもなって新しい環境で働くということはそう簡単に慣れるものじゃない。
毎日クタクタで終わる日々だ。
それこそ、ヘルパーさんがいなかったら体調を崩していることは間違いないないだろう。
俺はこれから母親が亡くなるその時まで、この生活を送ることになるのか…
「タカシ、気をつけてね」
そう無邪気な笑顔を向ける母さんに罪悪感を抱きながらも、「行ってきます」と微笑んで返事をする俺は悪い息子なのだろうか。
乗ってきたことろだったのに
~脳梗塞で右半身に後遺症が
残った母親の話~