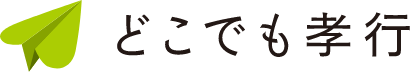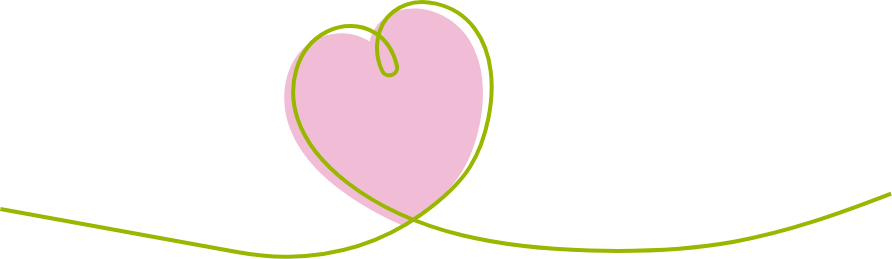介護保険制度の基礎知識5:介護保険制度とお金の話
40歳以上の人が毎月保険料を納め、やがて介護が必要になったときには1~3割の自己負担率で介護度に応じた介護サービスが受けられる日本の介護保険制度ですが、現実に介護が必要になったら、一体どのくらいお金がかかるものなのでしょうか。
ここでは、実際のサービスの費用や、自己負担金額について触れていきたいと思います。
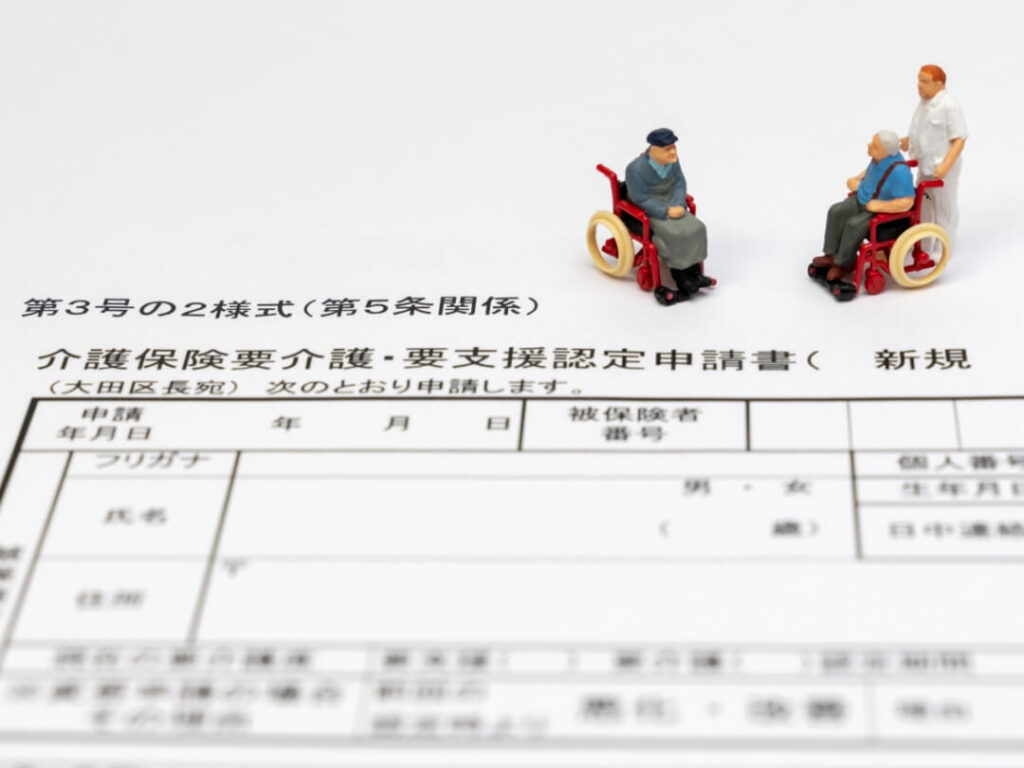
1.介護保険サービスにかかる費用
ではまず、主な介護保険サービスの費用がどのくらいなのかを見ていきましょう。
ここではサービスの単価(10割負担の場合の金額)を記載しています。
▶訪問介護(ホームヘルプサービス)
・身体介護中心(要介護1~5の人、20~30分未満) 2,762円
・生活援助中心(要介護1~5の人、20~45分未満) 2,022円
▶訪問入浴介護
・要介護1~5の人 13,923円/回
・要支援1~2の人 9,414円/回
▶訪問看護
・病院、診療所より訪問(30分未満) 4,397円(要介護)/4,210円(要支援)
・訪問看護ステーションより訪問(30分未満)5,193円(要介護)/4,972円(要支援)
▶訪問リハビリテーション
・要支援、要介護の人ともに 3,324円/回
▶通所介護(デイサービス)
・要介護1 6,995円 ・要介護2 8,255円 ・要介護3 9,570円
・要介護4 10,875円 ・要介護5 12,196円
いずれ1日(7~8時間未満)あたりの金額
▶通所リハビリテーション(デイケア)
・要介護1 8,200円 ・要介護2 9.715円 ・要介護3 11,255円
・要介護4 13,060円 ・要介護5 14,830円
いずれも1日(7~8時間未満)あたりの金額
・要支援1 22,233円/月
・要支援2 43,309円/月
▶短期入所生活介護(ショートステイ)
・要支援1 4,830円 ・要支援2 6,010円
・要介護1 6,454円 ・要介護2 7,205円 ・要介護3 7,985円
・要介護4 8,730円 ・要介護5 9,465円
いずれも多床室利用で1日あたりの金額
▶施設サービス
・特別養護老人ホーム 7,604円(要介護3)~9,045円(要介護5)
・介護老人保健施設 8,415円(要介護1)~10,712円(要介護5)
・介護医療院 8,811円(要介護1)~14,546円(要介護5)
いずれも多床室利用で1日あたりの金額
訪問サービスでは夜間・早朝・深夜などの訪問は割増料金の設定がありますし、通所サービスや施設サービスでは利用する施設の種類等によって金額が異なることもあるため、あくまでも目安にはなりますが、このようにどのサービスも、介護度別やあるいは回数や時間などの利用単位ごとに費用が設定されています。
利用者はこの費用のうちの1~3割を、自己負担してサービスを利用することになります。
また、通所サービスや施設サービスにおいては、食費や居住費(宿泊費)、日常生活費(身の回り品・理美容費など)はサービス費用には含まれていませんので、これらの費用も別途自己負担することになります。
2.所得によって変わる介護保険サービスの自己負担割合
サービス費用の目安がわかったところで、次は自己負担について説明していきます。
要介護認定を受けて介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、利用者によって1~3割と幅があります。
この負担割合はサービス利用者本人の所得によって判定基準が決まっており、要介護認定を受けた際の結果通知とともに交付される「介護保険負担割合証」に、決定した負担割合が記載されます。
65歳以上の第1号被保険者においては、以下のように一定以上の所得がある場合に、2割もしくは3割負担となります。
・合計所得金額160万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上(65歳2人以上世帯で346万円以上)⇒2割負担
・合計所得金額220万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上(65歳2人以上世帯で463万円以上)⇒3割負担
所得額が上記以下の第1号被保険者と、すべての第2号被保険者(40~64歳の方)は1割負担と定められています。
なお、この負担割合証の有効期限は1年間となっており、毎年8月に前年の所得に基づいて更新されます。
3.要介護度によって変わる支給限度額
要介護認定を受けて負担割合も決まったら、作成されたケアプランにそって介護保険サービスを受けていくことになるわけですが、サービスを受けるにあたって、1~3割の自己負担で利用できる金額には上限があります。
| 要介護度 | 支給限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
この限度額を超えてサービスを利用した部分については、全額自己負担ということになります。
〈例〉要介護1で自己負担割合が1割の方が、1カ月に170,000円分のサービスを利用した場合の自己負担金額は、
支給限度額167,650円の1割負担分 ⇒ 16,765円
限度額を超えた部分を全額負担170,000円-167,650円 ⇒ 2,350円
を合計した19,115円となります。
なお、特定福祉用具購入や居宅介護住宅改修、居宅療養管理指導など、支給限度額の範囲に含まれない(別途で上限額が設定されている)サービスもあります。
4.自己負担が高額になったときの軽減策
要介護度と負担割合ごとに、実際どのくらいの自己負担額になるのかを見てきましたが、では必ずこの額をすべて自己負担しなければいけないのかと言うと、そうとは限りません。
医療費における高額医療費制度と同じように、介護保険でも利用額が高額になった場合に利用できる負担軽減制度があります。
「高額介護サービス費」と言って、自己負担金額(1~3割負担)の合計が高額になった場合に、決められた限度額を超えた部分が後から給付される制度です。
| 区分 | 自己負担の限度額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 140,100円(世帯) |
| 年収約770万円以上~1,160万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯(年収770万円未満) | 44,000円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
| 上記のうち、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
ここで気を付けたい点は、高額介護サービス費の給付対象となるのはあくまでも支給限度額の範囲(1~3割の自己負担の部分)に対してである、というところです。
ですので、支給限度額を超えたサービス利用(自費利用)分の全額自己負担は変わりません。
〈例〉要介護1で自己負担割合3割、年収770万未満の住民税課税世帯の方が、
① 1カ月に165,000円分のサービスを利用した場合
165,000円の3割負担分 ⇒ 49,500円
上記のうち自己負担の限度額44,000円を超えた金額 ⇒ ▲5,500円
高額介護サービス費として5,500円が後から給付され、実質的な自己負担は44,000円となります。
② 1カ月に175,000円分のサービスを利用した場合
支給限度額167,650円の3割負担分 ⇒ 50,295円
上記のうち自己負担の限度額44,000円を超えた金額 ⇒ ▲6,295円
支給限度額を超えた部分の全額自己負担額175,000-167,650 ⇒ 7,350円
高額介護サービス費として6,295円が後から給付されるので、実質的な自己負担は限度額の44,000円と全額自己負担部分を合わせた51,350円となります。
このほかにも、医療費の自己負担額と合算して、年間で決められた限度額を超えた場合に超過部分が払い戻される「高額医療・高額介護合算制度」や、低所得者等に対する助成制度、災害の被災者などに対する特別な減免制度などもあります。
また、施設サービスや短期入所サービス利用時にかかるサービス費以外の食費や居住費(滞在費)に関しても、「特定入所者介護サービス費」という所得に応じた負担限度額の制度があります。
いずれの制度も給付や減免を受けるには個別の申請が必要となっていますので、対象に該当する際には申請を忘れずに行うようにしましょう。
介護はお金がかかる、というなんとなくのイメージによって、将来の介護に漠然とした不安を感じる方も少なくないのではないでしょうか。
費用負担や制度のしくみをしっかりと知ることが、あらかじめ将来に備えたり、あるいは実際に介護が必要になった際に自己負担を減らせるところはしっかりと減らしながら、必要なサービスが受けられるということにつながっていくのではないかと思います。